
『大 師 の 馬』
【主な登場人物】
弘法大師 お百姓さん夫婦
【事の成り行き】
え~、およろしぃおあとでございますが、男のあとへまた男、一人のあと
へまた一人で、どぉもこの代わり映えがいたしません。延々とこぉ一人ずつ
一人ずつ出て来るんでございますんですが。
どぉもこの一人といぅのはあんまり愛想がないんで、お漫才なんかでござ
いますと二人(ふたぁり)で出てまいりますからね、横を向いて話しかけると
向こぉから返事が返ってくる。
掛け合いでおしゃべりをいたしますからお客さま方のほぉも気が浮いてき
て、思わず「よッ(パンパンパン)」手の一つも叩こぉかといぅことになる
んですが。
もぉ、一人といぅのはねぇ、横向いたさかいいぅて誰がいてくれるわけや
なし、こっちゃ向いたさかいいぅて返事してくれる人があるわけやなしね、
一人でしゃべって一人で返事して、歌もうたわず屁もこかず、実にまぁ、愛
想のない商売で。
けどまぁ、これも決して悪気があって出て来るわけやないんで、これもみ
なみな……、やむを得ず出て来るよぉな仕掛けになってまして、あまり長い
お時間やございませんので、おあとお楽しみに最後までごゆっくりとお遊び
のほどを願いますが。
あの~、面白いもんですなぁ~、一人何か有名な人が出ると、全部そこへ
喰われてしまうといぅことがあります。昔から「大師は弘法に奪われ、奉行
は大岡に奪われる」ねぇ「大師は弘法に奪われ、黄門は水戸に奪われる」て
なことを申しますが。
あの水戸黄門「黄門さま」と言ぅと水戸のご老公といぅのがポンと頭にく
る。こら、芝居とか講談とか、あるいはあぁやってドラマになりますから、
黄門さまといぅと水戸のご老公といぅのがくるんです。
でもあの、黄門さまは水戸だけやないんですね、あれは中納言といぅ位の
方が隠居いたしますと、みな黄門さまになるんです。ですから、水戸中納言
光圀公がご隠居あそばして黄門さん。
そのほかにも中納言といぅ位はいろんな方があるんですからね、柳沢中納
言とかね、北白川中納言とか、中納言はいっぱいあるんですよ。エビでもね、
イセエビでも「中納言」てあるぐらいですから。
ですからこの、黄門さまでもいっぱいいらっしゃったんですが、単に「黄
門さま」と言ぅと水戸のご老公と、こぉいぅことになる。
お奉行さまでもそぉですな「名奉行」といぅと大岡越前守とこぉなります。
別にお奉行さま、名奉行と言われた人は大岡さまだけやないんでね、根岸肥
前守でありますとか、あるいはもっと身近なところで遠山の金さん、遠山左
衛門尉(さえもんのじょ~)景元なんてな、こら名奉行中の名奉行ですが。
どっちかといぅと遠山左衛門尉景元といぅよりは、こっちゃ、金さんのほぉ
が有名ですからね、どぉしても名奉行といぅと大岡越前守とこぉなるんです
なぁ。
で、この「お大師さま」がそぉです。伝教(でんぎょ~)大師、達磨大師、
沢庵(たくわん)禅師、禅師は別ですが……、いろんなお大師さんがあります
が、単に「お大師さん」と言ぅと弘法大師とこぉなる。
有名になりたいもんですなぁ、また弘法大師といぅ人はね、いろんなこと
をして歩いてますから有名にならざるを得んのですね。器用な人ですから、
もぉあの方はいろんなことがおできになった。
日本三名筆の一人と言ぅぐらいですから「色は匂えど散りぬるを、我が世
誰ぞ常ならむ、有為の奥山今日越えて、浅き夢見じ、酔ひもせず」いろは四
十八文字といぅのをお作りになったのが、この弘法大師。
ですから、この方もぉ筆を持たせたら右に出る人はないと申します。字に
ついてはものすごくご堪能で、字ぃだけやないです、いろんなことして回っ
てますです。お大師さまといぅ人はね、ズッと歩き回ってるんですよ、あれ
暇なんですよ、よっぽどね。
四国中歩き回って「四国八十八箇所」それで足りないから西国を回って、
これまた「西国八十八箇所」歩き回ってる。それだけやないんですよ、あっ
ちこっちで橋をかけたりね。
「橋かけた」て、何もあんた弘法大師が自らカンナ持って削ったわけやな
いんですよ、あれ、橋かけたんはみな大工さんがかけたんですがね。それで
も「弘法大師が橋かけた」と、こぉ申します。
でまた、弘法大師といぅ方はいろんなパフォーマンスができたんですな。
ご修行のみぎり喉が渇いたといぅので杖で一つトンッ、お突きになりますと、
そこから水が湧いてきた「大師手向けの水」
もぉこんな杖は要らないといぅので、杖を突き刺してお帰りになると、そ
の杖から根っこが生えて大きな桜の木になった、とかね。いろんなことをす
るんですなぁ。
そぉかと思いますと、文字のほぉでもそぉですなぁ、京都の御所の応天門
といぅ門ができあがったときに、扁額、門の上へこぉ額を上げます「応天門」
と書いて額をお上げになった。
ところが「弘法も筆の誤り」といぅんで、この上へ上げてしまいましてか
らヒョイと気が付くと、応天門の「応」の上の点が一つ忘れてあった。ね、
点が一つ足りない「てんでものにならない」とはこれから始まった。
「あれをもぉいっぺん下ろして書き直すといぅと、大変な大事業である」
と言ぅていると、弘法大師が「でわ、筆と墨を用意してくれ」墨をたっぷり
磨りまして、この筆に含まして、下から上をめがけて「いやッ!」
お投げになりますと、この筆がツ~ッと飛んで行って、ポ~ンと当たった
ところに点が入ったといぅんですな「弘法の投げ筆」何でもできる人なんで
すなぁ。あの人は今生きてりゃね、大変なもん、寄席へ出たらゴッツイ金儲
けでっせ、あれ。
いろんなことがでけたんです。でこの、弘法大師がある日、町を歩いてま
すと、横のほぉから竹カゴ、ザルですな、あれ我々大阪のほぉでは「笊(いか
き)」てなことを言ぃますけども、お台所で使いますザル、このザルがうつ伏
せになって横丁からツツツツ、ツ~ッ!
「あれ? 俺もたいがいいろんなことをするけれども、竹カゴが駆け出し
て来るといぅのは初めて見た。こんなもんに足があるわけでもなし、どっか
らこんなもんが駆け出して来たんか知らん?」
じっとご覧になってると、この竹カゴがそ~ッと持ち上がって、下から可
愛ぃ仔犬が顔を出したんで「あぁ、こんなやつがカゴの下に入っていたのか、
ハッハッハッハッ、仔犬が顔を出して可愛ぃものじゃな」と、お笑いになっ
た。
と、この時にはたと気が付く「あぁそぉか、竹カゴの中から仔犬が顔を出
したのを見て笑ぉた。カゴの中から犬が出て笑ぉたによって、竹冠の下に犬
と書いて笑うと読んだらよかろぉ」と、ここであの「笑」といぅ字ができた
んです、竹冠の下に犬と書いて、ね。
「これだけのことを教えてくれたこの仔犬に、何か礼をしてやりたいが」
ヒョイとご覧になると、その頃は犬は三本足やった。いえいえ、ホンマでっ
せ、その時代があったんです。こら、うちの爺さんに聞ぃたんですから間違
いない。
ところがね、その頃は五徳、五徳ご存知ですかねぇ? あの、火鉢ん中に
入って、上へ茶瓶が乗っかるね、いえいえ、こないだもね、わたしこの噺し
てましてね、この五徳の噺をすると前にいたアベックがね、この頃アベック
言わないんですな、前にいたツーショットが、女のほぉがね、男の子に「五
徳てなに?」て聞ぃてるのん。
そぉいぅのて、こっちは一方通行ですから、お客さま方のほぉ向いてしゃ
べってりゃえぇんですけど、そぉいぅのて妙に気になるんです、客席の声と
いぅのはね。ですから、思わずヒョイッと見ると「五徳てなに?」
「五徳知らんのん?」て言ぅたら「知らん」「あのねぇ、火鉢知ってる?」
「うん」「あの火鉢の中にね、灰が入ってるでしょ灰が、いやいや、夏飛ん
でる蝿(はい)やないの、白い粉……、炭が燃え尽きて、炭知ってる? 炭知
らんのん? 磨って字ぃ書く墨やないねん、燃やす炭、炭知らん? 知らん
のん? あのねぇ、山に木ぃ生えてまっしゃろ……」
そっから説明して灰が分かって、五徳がやっと分かった頃には、わたしもぉ
落語やる時間無くなったんです。で、今日は皆さま五徳をご存知のものとし
て、噺を前へ進めたいんでございますが。
でも、皆さま方がご存知の五徳てな三本足なんですよね、曲がった鉤の手
みたいな物が三本付いてますでしょ、下の輪っかのとこに、で、こぉ茶瓶が
乗っかる。あれねぇ、昔はあの五徳の足が四本やったんです。そのほぉがまぁ
茶瓶は掛かりやすいんでしょ~けども。
で、犬が三本足の頃には、この五徳が四本足やった。それをご覧になった
弘法大師が「五徳は三本足でも茶瓶は乗っかる、犬が三本足ではこら歩きに
くい、可哀相である」といぅんで、五徳の足を一本取って犬にあげたんです。
それから犬は四本足になって五徳が三本足になったんです。アハハ、てホ
ンマですよこれ。それで犬のほぉもね、それだけの恩義は心得てますから、
「せっかく、弘法大師にいただいた足、不浄で汚してはいけない」といぅん
で、犬はションベンするとき片足上げる。
これ、何よりの証拠でございます。こぉいぅことはね、よそ行って言わん
ほぉがよろしぃよこれは。
弘法大師といぅ方はそぉいぅ具合にいろんなことがおできになって、いろ
んなところをお回りになった。それにまた、弘法大師といぅ方は情け深い方
ですから、困ってる人を見るとね、放っておけないんですね。
お若い頃には空海とおっしゃってね、遣唐使、船に乗って中国へ渡ってい
ろんなお経やなんかを日本へ持って来た、それぐらいの人でございますから、
巷を歩いておりましても、お腹の空いた人なんかを見るとね、もぉ放ってお
けない。
自分のお腹の空いてるのも忘れて、お弁当なんかでもすぐその人にあげて
しまう。お腹の空いた人を見ると、自分の弁当を「食ぅかい?」
ですからね、その日も弘法大師が巷を歩いておりまして、例によりまして
自分のお弁当を人にあげてしまう。お腹が空いてしょ~がない「これはえら
いことをしたなぁ、どっかで食べるものを頂戴しなければいけないな」と思
いながら歩いてまいりますと、川っぷちで一人のおばさんがお芋を洗ってま
してな。
「あ~、これこれ婆さん、卒爾(そつじ)ながらひとつ頼みがある」ここな
んです、弘法大師ほど偉い人でも、ここで女心が分からなかった「これこれ
婆さん」と声をかけたのが悪かった、おばさんですからなぁ。ここを「これ
これお姉さん」と言えば「はいッ!」と言ぅたんでしょ~けど。
自分では、まだ若いつもりのおばさんに「これこれ婆さん」と言ぅたばっ
かりに「なんぬかしてけつかんねん、この乞食坊主」と、こぉ向こぉは思た
んですなぁ。
■卒爾ながら空腹で難儀をいたしておる、その芋を一つ分けてもらうわけにはいかぬかな?
●(誰がそんなもんやるかい……)あの~、
お坊さま、せっかくでございますけども、
これは人間の食べる芋ではございませんで。
人間の食べる芋ならば幾らでも差し上げますが、
これは馬の餌でございます。
●馬の食べる芋で、人間は食べられませんので
■おぉ、さよぉかな、これは卒爾なことを申した、
いや御免ごめん。
ならば結構。
向こぉ行ってしまいよった。
あとで綺麗にお芋洗ろて蒸(ふ)かしまして、
ちょ~どお芋が蒸かしあがったところへ亭主が野良から帰って来て、
▲おい、嬶(かか)帰った。腹空いてんねや
●ちょ~ど帰って来る頃やと思て、
お芋さんが蒸かしてあんのん、
まぁまぁ、お上がり
▲そぉか、ほなよばれよか。
芋を一口パクッと食べた途端に、
家鳴り振動ガラガラガラガラ、ガラ~と大きな物音がしたかと思いますと、
この亭主が「ヒヒヒ、ヒヒ~ンッ」て、
馬になったんです。
●んまぁ~ッ、えらいこっちゃ、何でこんな……、
さてはさっきのお坊さまが、
きっとアラタカなお方であったに違いがない。
あの方に「馬に食べさす芋や」と言ぅて嘘をついたばっかりに、
こんなことになったに違いがない。
あのお坊さんを呼び戻さなければ……(ダダダダ、ダ~ッ)
●もぉ~しぃ~、お坊さまぁ~、ちょっとお待ちくださいませぇ~ッ
■愚僧かな?
●お坊さまでございます、どぉぞ相すみませんことで、
先ほどついうかっといたしまして「馬が食べる」と嘘をつきました。
●嘘をついたわたくしが悪ございます、どぉぞお戻りくださいませ。
お芋は幾つでも差し上げます、
どぉぞひとつ亭主を許してやっていただきとぉございます
■いきなりそぉ申されても、愚僧には見当が付かん。
ご亭主がどぉかなされたかな?
●「どぉかなされた」ではございません、
わたくしがあの「馬に食べさせる芋」と申しましたからでございましょ~か、
帰ってまいりまして亭主があの芋を一口食ぅなり、
馬になってしまいました。
■馬になった、それはお困りじゃな
●えぇ、こらお坊さま、あなたが罰(ばち)を当てた
■わしはそのよぉな通力はない、
だいちわたしがその人に罰を当てるといぅよぉなことがあろぉはずがない。
そら、あなたが妄語戒をおかしたによって、
こら仏さまの天罰が当たったものとみえるが、
愚僧ではどぉもできん。
●そんなことおっしゃらんとどぉぞ、あなたのせいでございます。
こぉやって謝っているんでございます、
どぉぞお戻りになって、亭主を元の人間に戻していただきとぉございます。
■そのよぉなことが、愚僧にできることかできんことか……、
まぁ戻ってみましょ~。
戻ってまいりますと、いかさま、栗毛の馬がそこんとこで
「ヒヒ~ン、ヒヒ~ン」
と嘶(いなな)いております。
■これがご亭主かな、あぁ、ならばできることかできぬことか、
祈って進ぜましょ~。
おんあぼきゃべぇろしゃのぉまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん、
おんあぼきゃべぇろしゃのぉまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん……
一心に呪文を唱えながら、数珠で馬をこぉお撫ぜになります。
顔のところを撫ぜてやりますと、馬の顔がツツツツ、ツ~ッと縮んで人間の顔になった。
●おぉ、おぉ、亭主の顔になりました。
どぉぞ、もっとよろしくお願いいたします
■おんあぼきゃべぇろしゃのぉまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん、おんあぼきゃべぇろしゃのぉまかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん……
首筋を撫ぜてやりますと、
首がツツツツ、ツ~ッ。
前足のところを撫ぜると、これがス~ッと立ち上がって手ぇになった。
胸のところが人間に、お腹のところが人間になります。
もぉ少し下へ行こぉとすると、このおばさんが、
【さげ】
●あぁ~ッ、お坊さま、そこはそのままにしておいてください。
【プロパティ】
黄門=中納言の唐名。
徳川光圀=(1628~1700)江戸前期の水戸藩主。頼房の三男。幼名千代松。
字(あざな)は子竜、号は梅里(ばいり)。諡号、義公。世に水戸黄門と
も。大義名分を重んじて儒学を奨励、彰考館を設けて俊才を招き「大
日本史」を編纂。希代の名君と賞され「水戸黄門漫遊記」による逸話
が広く流布している。が、そのほとんどは明治時代に上方の講釈師が
作り上げたという。
イセエビでも「中納言」=活伊勢海老料理を売りにする飲食店グループ、
株式会社中納言。本社、兵庫県西宮市本町。昭和25年9月創業。
大岡忠相(おおおかただすけ)=(1677~1751)江戸中期の幕臣。8代将軍徳
川吉宗に抜擢されて江戸町奉行となり越前守と称す。公正な裁判とす
ぐれた市政で知られた。のち三河西大平の大名となった。
根岸肥前守衛奮=新潟奉行・奈良奉行・外国奉行・勘定奉行・大目付・勘
定奉行・江戸南町奉行・講武所奉行並・関東郡代・一橋家家老など幕
府の要職を歴任した。
遠山金四郎=遠山景元(とおやまかげもと)1793(寛政5)年8月23日~1855
(安政2)年2月29日。江戸時代の旗本で、天保年間に江戸北町奉行、
後に南町奉行を勤めた人物。演劇・ドラマ「遠山の金さん」のモデル。
伝教大師=最澄(767~822)日本天台宗の開祖。比叡山延暦寺を開山。
達磨大師(だるまだいし)=達磨の尊称。中国禅宗の祖。南インドの王子と
して生まれ、般若多羅から教えを受け中国に渡って禅宗を伝えた。少
林寺で9年間面壁したといわれる。5世紀末から6世紀末の人とされ
る。円覚大師。
日本三名筆=空海、橘逸勢、嵯峨天皇。
卒爾(そつじ)=突然であること。注意や思慮を欠くこと。失礼なおこない
をすること。
卒爾(そつじ)ながら=突然、失礼とは存じますが。
何をぬかしてけつかんねん=ぬかして+けつかる+ねん。ヌカスは「言う」
ケツカルは「する、いる」という意味の下品な悪態口を示す語。ネン
は助詞「~のだ」標準語では「何をおっしゃっているのでしょう」。
なんぬかしてけっかんねん。
あらたか=神仏の霊験や薬のききめが著しいさま。
通力=禅定などを修めた結果得られる、何事も自由自在になし得る超人的
な力。神通力。禅定:精神をある対象に集中させ、宗教的な精神状態
に入ること。また、その精神状態。
天台宗五戒=1.不殺生戒(生命あるもの傷つけず大切にする)2.不偸
盗戒(与えられないものを取らない)3.不邪淫戒(淫行を遠ざけ、
不倫をしない)4.不妄語戒(嘘をつかない)5.不飲酒戒(酒など
の嗜好品におぼれない)
いかさま=相手の言葉に賛意を表す語。なるほど。いかにも。
おんあぼきゃ~べぇ~ろ=真言宗:光明真言おんあぼきゃべいろしゃのう
まかぼだらまにはんどまじんばらはらばりたやうん(心を込めてお祈
りいたします。この世に満ち溢れているすばらしい命の輝きよ、限り
ないその働きよ、智慧の宝珠と慈悲の蓮華との救いの光明を差し伸べ
てください。どうぞお願いします)
音源:露の五郎(五郎兵衛) 1997/08/05/鈴本演芸場
面白画像 ジョーク に参加中クリックをお願いします
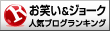 ブログランキング
ブログランキング