
「人類滅亡、12のシナリオ」と題したレポートが世界に衝撃を与えている。人類を不妊にする超汚染物質、地球を飲み込む人工ブラックホール…。こんな想像をはるかに超えた内容も含まれるが、発表したのが英オックスフォード大など名だたる研究機関の関係者とあって、ただのSF(サイエンス・フィクション=科学的な空想)と片付けるわけにもいかない。むしろ「リスク管理のヒントに」と評価する専門家もいる。果たして、その気になる衝撃のシナリオとは-。(土塚英樹)
詳細な分析
レポートが公表されたのは今年2月中旬。作成者にはオックスフォード大や、傘下のフューチャーヒューマニティ研究所の科学者、スウェーデンのグローバルチャレンジ財団の専門家、ビジネス分野の将来リスク分析などを手掛ける専門職「アクチュアリー」ら錚錚(そうそう)たるメンバーが名を連ねた。
200ページを超える分量の報告書は、人類滅亡の12のシナリオを具体的に4ジャンルに分類。それぞれに詳細な分析を加えている。
まずは「現在進行中のリスク」のジャンルとして、地球温暖化など極端な気候の変化が飢餓を生み、社会崩壊による移民増加などをもたらす「極端な気候変化」や、人の往来の激しさやスピードが増し、発生の可能性が高まっている「世界規模のパンデミック(感染症の大流行)」、世界経済がグローバル化して経済危機や貧富の差の拡大が起こりやすくなり、大きな社会混乱や無法状態をもたらす「国際的なシステムの崩壊」など5つのシナリオを挙げている。
また、「外因的なリスク」のジャンルには「巨大隕石の衝突」と「大規模な火山噴火」の2つのシナリオ、「国際政治のリスク」ジャンルには「政治の失敗による国際的影響」のシナリオを指摘した。
さらに「新たなリスク」ジャンルとして、ゲームや映画になったテーマでもある「バイオハザード」の世界として人工的な病原体の生成など「合成生物学」と、小型核兵器などの開発に転用される可能性がある「ナノテクノロジー」、映画「ターミネーター」のように膨大なロボットが人類に反逆する「人工知能」のシナリオのほかに、「その他の全く未知の可能性」も挙げられた。
レポートの狙いは
この最後にある想定を超えた「その他の全く未知の可能性」とは一体何か-。
報告書では、具体例として「人類を不妊にする超汚染物質の開発」や「人工ブラックホールが開発され、地球を飲み込む」「動物実験により、人類を超える知能をもつ生物が出現」「誰かが地球外生命(ET)にコンタクトし、危険な異星人(エイリアン)の注意を呼び寄せる」などを挙げている。
ここまでくると、もはやSFの世界にすぎないと片付けたくなるが、レポートを詳しく分析したニッセイ基礎研究所研究員、安井義浩氏は「われわれが、ときどき酒場で酔っ払ってする話とは大きく違う」とした上で、「過去には『ばかげている』と考えられていたことが、現実の脅威になっているケースもある。どんな可能性も否定できない」と注意を促す。
そのうえで安井氏は「このレポートの本質的な狙いは、リスクに対処する行動と対話を促すことにある」と指摘する。
実際に報告書はリスクへの対処法として10項目を紹介している。
具体的には、「世界規模のリーダーシップ・ネットワークを構築する」「危険探知システムを構築する」「極度に複雑な社会システムを視覚化する」「地球規模のリスクに対する指標を政府が確立する」などだ。
さまざまな思惑も交錯
12のシナリオが発表されると、たちまち世界に衝撃が広がり、日本でも「(10月に個人番号の通知が始まる)マイナンバー制度が(絶滅シナリオの)布石になる」などと、さまざまな憶測がインターネット上などで早くも飛び交っている。
ただ、安井氏は今回の12のシナリオについて「個人や企業ではどうにもならないものもある」と冷静な対処を促す。
実際、レポートでも「国際政治のリスク」について「人間のやることであって、防いだり、各国が協力したりすることも比較的やさしい」とする一方、「隕石、噴火などは防ぎようがないが、被害を少なくすることはできるかもしれない」と指摘。「もっとも厄介」なリスクとしては人工知能のリスクを挙げ、「いったん暴れだしたら、生身の人間には止められない」としており、数々のリスクを対処可能なレベル別に分類している。
安井氏は、絶滅のシナリオ自体よりは、むしろ10項目の対処法の方に注目しており、「少しスケールを小さくして、自分、あるいは会社などの通常のリスク管理にあてはめて考えれば、何か(解決などの)ヒントになることがあるのではないか」と話している。
産経ニュースへ 産経WESTへ このニュースの写真
 関連ニュース
関連ニュース
 【経済裏読み】“暴落相場”ちゃっかり売り抜け 中国富裕層、“政府宣伝”に躍らず “頭脳流出”で市場当局も素人?
【経済裏読み】“暴落相場”ちゃっかり売り抜け 中国富裕層、“政府宣伝”に躍らず “頭脳流出”で市場当局も素人?
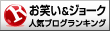 ブログランキング に参加中クリックをお願いします
ブログランキング に参加中クリックをお願いします


















